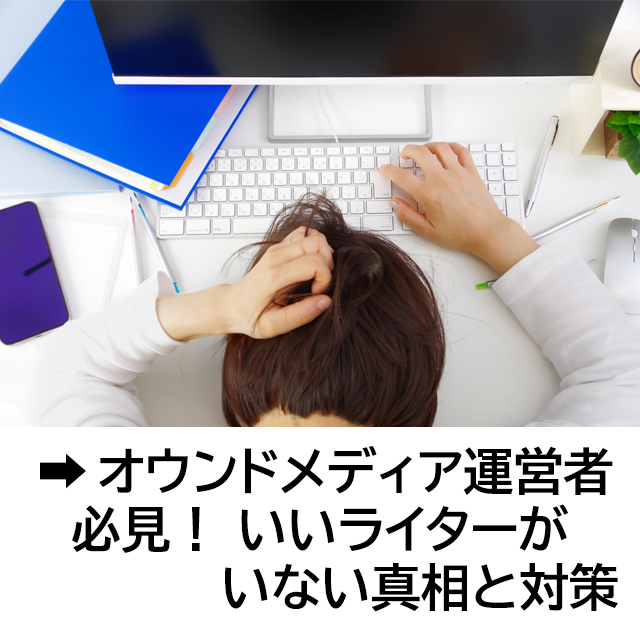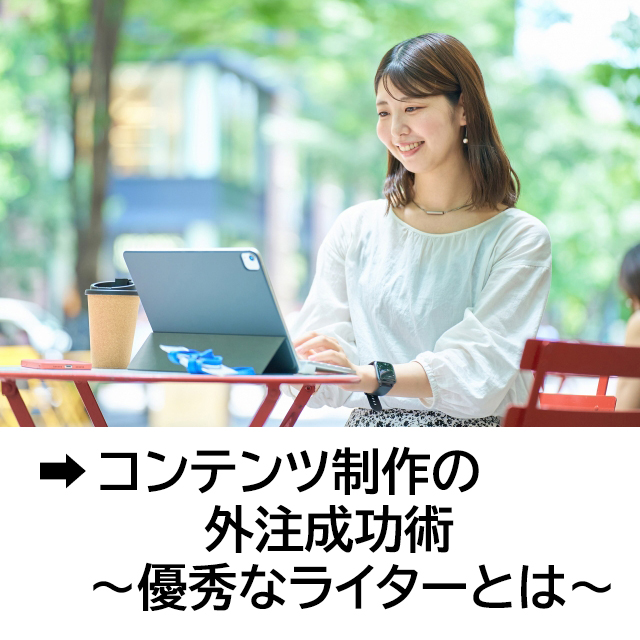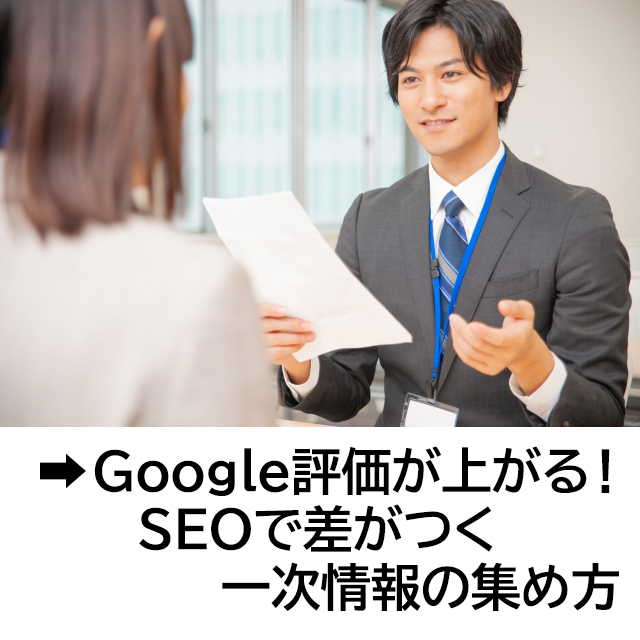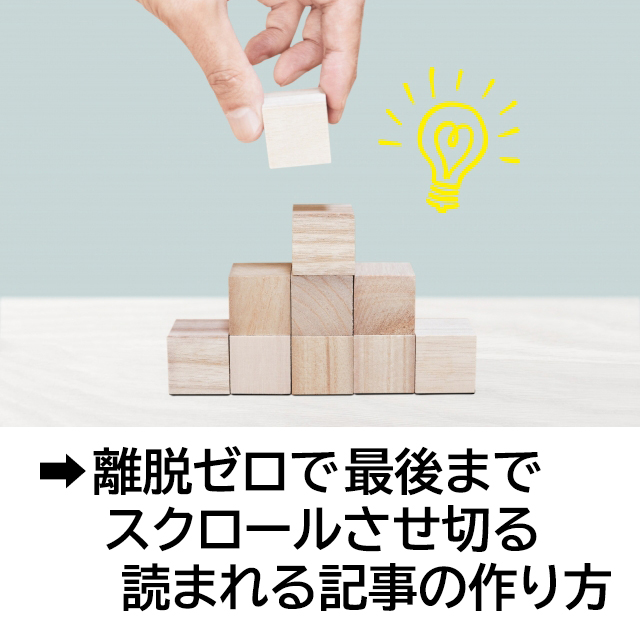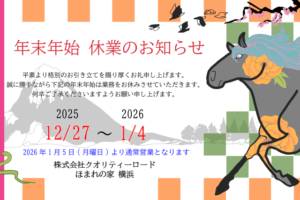Google評価が上がる! SEOで差がつく一次情報の集め方
オウンドメディアの記事を書いていて、
「構成まではできたけど、このあと何を集めればいいの?」
そんなふうに手が止まったことはありませんか?
構成は、記事の「設計図」のようなもの。
でも、その中に入れる素材が浅いと、どれだけ整った構成でも、読み手には「ふつうの記事」として流れてしまいます。
では、どうすれば「伝わる記事」になるでしょうか?
ヒントは、「一次情報」にあります。
自分たちの経験、現場の声、社内での気づき——
そうしたオリジナルの情報こそが、記事の信頼と深みをつくります。
AIで文章をつくることが当たり前になった今、「人の目線でしか語れない情報」を集められるかどうかが、差を生む時代です。
この記事では、構成を作った「その次のステップ」として、記事の質を一段引き上げる素材集めの方法を整理していきます。
どんな経験を掘り起こせばいいのか。
どんなアンケートや取材で情報を深めればいいのか。
次の章では、その「一次情報の見つけ方」から見ていきましょう。
「一次情報」がコンテンツマーケティングの信頼をつくる

構成案をつくったあとに、まず考えたいのが「どんな素材を集めるか」です。
しかし、ここで多くの担当者がつまずいてしまいます。なぜなら「どんな情報なら価値があるのか」が、あいまいなままだからです。
たとえば、インターネット上にすでにある記事をまとめ直して、図解を加えたり、言い回しを少し変えたりすれば、それなりに「それっぽい記事」は完成します。
けれど、それは「一次情報」ではなく「二次情報」。いわゆる「こたつ記事」と呼ばれるタイプのものです。
以前なら、そうした記事でも検索上位を狙えました。
しかし今は、Googleの品質評価が大きく変わり、「誰が、どんな経験にもとづいて書いたのか」が問われる時代に変わりました。
Googleが評価軸として重視しているのが「E-E-A-T」――
- Experience(経験)
- Expertise(専門性)
- Authoritativeness(権威性)
- Trust(信頼性)
つまり「実際に体験している人の言葉」が、何よりも信頼されるようになったんです。
たとえば、
- 「SEO 対策 やり方」をまとめた一般的な記事
よりも、
- 「自社サイトのSEO改善でCVRを1.2倍にした実践記録」
のほうが、明らかに価値があります。
後者には、「現場の数字」「使ったツール」「試行錯誤の経緯」といった「その人にしか語れないリアル」があるからです。
検索エンジンはもちろん、読者だって、そこにこそ信頼を感じます。
そして、この「一次情報」は、どの企業にも必ず眠っています。
日々の業務の中で得られる小さな改善の記録、社内のノウハウ、顧客との対話、成功の裏にある失敗――
これらはすべて、かけがえのないオリジナルデータです。
AIが進化して、文章を簡単に生成できるようになった今、「情報の整理」だけでは誰でも同じ文章を書けてしまいます。
だからこそ、「人の目で見て、人の手で掘る」素材が重要なんです。
たとえば、あなたの会社で新しいツールを導入したとします。それを記事にするとき、「導入しました」だけでは一次情報になりません。そこに
「なぜそのツールを選んだのか」
「実際に使ってみてどんな課題があったか」
「導入前後でどんな数字の変化があったか」
を加えるだけで、記事の温度と解像度は一気に上がります。
読者が求めているのは、「一般論」ではなく「体験談」。
AIでは再現できない「その瞬間の空気」を伝えられるのは、人の言葉だけです。
つまり、一次情報とは「真実の温度を持つ素材」。
企業がどんなに立派なミッションを掲げても、そこに「人の視点」がなければ、読者の心には届きません。
そして、これはすべての業種に共通します。
- 製造業なら、現場スタッフが語る作業改善の工夫。
- 教育業界なら、生徒や保護者の声。
- BtoBサービスなら、導入企業の成功事例。
どれも立派な一次情報です。
こうして見てみると、一次情報とは、特別な取材や大きな調査がなくても、日々の仕事の中からいくらでも見つけられるものなんです。
AIが書く「整った文章」は増えていきます。でも、人が書く「温度のある文章」は、減っています。
だからこそ、私たちは「人の体温が伝わる情報」を発信していく必要があるんです。
では、あなたの会社に眠っている一次情報はどこにあるでしょうか?
次の章では、その答えを探すために「経験を棚卸しして掘り起こす方法」を、見ていきましょう。
経験を棚卸しして掘り起こす — 一次情報の集め方と整理術

では、ここからはいよいよ「どうやって一次情報を集めていくか」を見ていきましょう。
いちばんの基本は、自分たちの経験を棚卸しすることです。
「棚卸し」と聞くと、少し難しそうに感じるかもしれません。
でもやることはシンプルで、これまでの取り組みを
「なぜやったのか」
「何をしたのか」
「どうなったのか」
「そこから何を学んだのか」
この4つに分けて整理するだけです。
一次情報を引き出す4ステップ
ステップ1 前提(なぜやったのか)
まずは、その行動に至った背景を思い出します。
たとえば「問い合わせ数が伸び悩んでいた」「季節商戦の前に改善したかった」など。
動機や当時の状況を整理しておくと、読者はその取り組みの意味を理解しやすくなります。
ステップ2. 実施(何をしたのか)
次に、実際にどんなことをしたのかを具体的に書き出します。
使ったツール、行った施策、チームの体制など、できるだけ細かく。
ここではスクリーンショットや社内資料などを残しておくと、後から数字の裏づけを取るときに役立ちます。
ステップ3. 結果(どうなったのか)
取り組みの成果をできるだけ定量的に整理しましょう。
たとえば「コンバージョン率が1.0%から1.2%に改善した」など。
数字で書くことで、記事全体の信頼度がぐっと上がります。
もし具体的な数値が出せない場合は、
「問い合わせ内容の質が変わった」
「顧客からの反応が明確になった」
など、変化の方向性だけでも構いません。
ステップ4. 学び(何を得たのか)
最後に、その経験から得た気づきをまとめます。
ここでは「感じたこと」だけでなく、「次にどう活かすか」を言葉にするのがポイントです。
「次回はアンケート項目を減らす」
「週次で結果を振り返る」
など、具体的な行動に落とし込むと、読者にとっても自分にとっても価値が残ります。
悪い棚卸しと良い棚卸しの違い
たとえば「LP(ランディングページ)の改善」というテーマで考えてみましょう。
悪い棚卸しの例
ユーザーインタビューを5人に行い、キャッチコピーを変更したところ、
コンバージョン率が1.2倍になりました。やはりユーザーの声は大切だと感じました。
この書き方だと、「なぜその施策を行ったのか」「なにが背景にあったのか」がわかりません。
情報としては正しくても、読者にとっては「ストーリーの温度」が伝わらないんです。
では、良い棚卸しの例を見てみましょう。
良い棚卸しの例
WebデザインスクールのLP改善を行いました。
もともとコンバージョン率は約1.0%で、決して悪くはなかったのですが、
繁忙期を前に歩留まりを上げたいと考え、ファーストビューを見直すことにしました。
5名のユーザーにインタビューしたところ、「他社との違いが伝わらない」という声が多く、
キャッチコピーを変更した結果、CVRが1.2%に改善。
月間で約2万人が訪問するページなので、+0.2%の改善で約40件の申し込み増、
売上に換算すると500万円以上のインパクトがありました。改めてユーザーインタビューの重要性を実感し、
今後は繁忙期ごとに定期的な調査を実施することにしました。
このように、「前提」→「実施」→「結果」→「学び」の流れで整理すると、
読者にも自分にも伝わりやすい一次情報になります。
「証拠化」で信頼を積み上げる
一次情報の信頼度をさらに高めるために、可能な範囲で「証拠」を残しておきましょう。
- 数字:アクセス解析やCV数などの定量データ
- スクリーンショット:ツールの画面、SNSの投稿、改善前後の比較
- 引用元:公的データや公式サイトの情報
こうした素材をそろえておくと、後から編集チームやデザイナーに共有する際にもスムーズです。
「どこをどう改善したのか」が可視化されることで、チーム全体で「学びを再現できる記事」をつくることができます。
一次情報は、特別な取材をしなくても、社内のあちこちに眠っています。
日報や会議メモ、施策の報告書の中にも、貴重な経験が詰まっているはずです。
だからこそ、まずは自分たちの中にある素材を整理すること。
それが、信頼される記事の第一歩です。
次の章では、その棚卸しで見つけた素材をもとに、外部の声をどう取り入れて深めていくか。「アンケート」と「取材」で情報を磨く方法をお伝えします。
アンケートと取材で深掘る — 編集者の仕事術で精度を上げる

一次情報の素材は、自分たちの中だけにあるとは限りません。
社内での棚卸しを終えたら、次は「社外の声」を取りにいく段階です。
つまり、アンケートと取材です。
どちらも目的はひとつ。
他者の経験や考えを通して、自社では気づけない視点を加えること。
ここで得られる情報があるかどうかで、記事の厚みがまるで違ってきます。
アンケート設計の要点 — 「削る勇気」で回答率を上げる
アンケートを作るとき、つい「あれもこれも聞きたい」と項目を増やしてしまいがちです。
でも実は、それが一番の落とし穴。
「せっかくだから」と加えた質問は、たいてい使われません。
そして、質問数が増えるほど離脱も増えます。
だからこそ、最初に「本当に必要な質問だけ」を残す勇気が大切です。
たとえば、次のようなアンケートを考えてみましょう。
対象:全国のデザイナー
目的:勉強方法を知ること
このとき、「年齢」「性別」「都道府県」といった属性質問を入れたくなりますよね?
でも数十件程度の回答数であれば、クロス集計しても意味のある傾向は出ません。
それよりも、
「今どんな方法でスキルを磨いているのか」
「役立った本は何か」
といった行動に直結する質問を優先したほうが有益なデータが得られます。
また、設計したアンケートは必ず自分で回答してみましょう。
1回ではなく、最低3回。
実際に答えてみると、
「この質問、前の項目と重なってるな」
「順番がわかりづらいな」
といった違和感が必ず出てきます。
この「自分で試す工程」が、離脱率を下げ、データの質を高める最短ルートです。
取材準備の第一歩 — 「相手を調べること」が信頼を生む
取材で大切なのは、質問を考える前に、相手を深く知ることです。
- 相手が書いた記事
- 出演したイベント
- SNSでの発信
できる限りすべてに目を通します。
それだけで、取材当日の空気がまるで違ってくるんです。
たとえば、SNSで「最近お子さんが生まれました」と投稿していた人なら、最初の雑談で「育児とお仕事の両立、大変ですよね」と声をかける。
そのひとことだけで、場がやわらぎ、話がスムーズに始まります。
また、事前に質問項目をしっかり作り込み、共有しておくことも欠かせません。
相手は忙しい中で時間をつくってくれています。
「今日は何を聞かれるのか」がわかっていれば、安心して臨めるんです。
取材中の工夫 — 「盛り上げ」と「深掘り」のバランス
取材の現場で心がけたいのは、情報を「引き出す」よりも「盛り上げる」こと。
相手が気持ちよく話してくれると、自然と一次情報の深い部分が出てきます。
一方で、表面的な言葉にとどまらないようにする工夫も必要です。
たとえば、「マーケティングは顧客理解が大事」と言われたとき。ここで「そうですよね」と流してしまうのはもったいない。
「そう感じたのは、どんな場面でしたか?」
「顧客理解を実践するために、社内ではどんなことをしていますか?」
こうやって抽象的な言葉を具体に落とす質問を重ねると、記事として効果的な「血の通った言葉」がどんどん集まります。
また、話が脱線することもありますが、それも悪いことではありません。むしろ、脱線の中にこそ本音や印象的な言葉が隠れていることも多いのです。
ただし、残り時間が少なくなったら、「すみません、あと15分ほどになってしまいました」と伝えて、優先度の高い質問に戻す。
この切り返しだけで、相手との信頼感は崩れません。
「自分が聞きたいこと」を聞く勇気
最後に、もうひとつ大切なこと。
取材では「相手にとって都合のいい質問」だけで終わらせないことです。
「自分が本当に知りたいこと」を聞く。
それが、取材を通して一次情報を掘り起こす最大のコツです。
たとえば、他のメディアで誰も聞いていない視点を投げかけてみる。
「なぜそう思ったのか」
「その決断に迷いはなかったのか」
こうした質問は、相手にとっても新鮮な問いになります。
「自分が心から知りたい」と思って聞く質問には、自然と温度が宿ります。
そしてその温度こそが、読者にも伝わるんです。
アンケートや取材で集めた情報は、記事を「整える」ためのものではなく、記事に「命を吹き込む」ためのものです。
社内の棚卸しで得た経験に、社外の声をかけ合わせる。
その掛け算が、読者にとってリアルで立体的な記事を生み出します。
次の章では、ここまで集めた素材をどう活かし、記事全体の構成に落とし込んでいくのかをまとめていきます。
まとめ 素材集めとは「現場の知恵を言葉に変えること」

ここまで見てきたように、良い記事は「きれいに書かれた文章」から生まれるのではありません。
本当に読まれる記事は、現場で生まれた知恵や声を、ていねいに言葉へ変えていく過程から生まれます。
一次情報とは、数字や記録のことだけではありません。
そこには、実際に手を動かした人の実感、悩みながら見つけた工夫、そして、誰かと交わした一言の中にある「リアルな感触」が含まれています。
つまり、一次情報=経験 × 声 × 対話の積み重ね。
この3つがそろったとき、記事には「自分たちにしか書けない温度」が宿ります。
AIがどれだけ進化しても、数字の裏にある想いや、現場の空気までは再現できません。
なぜその判断をしたのか、
なぜその一文が生まれたのか。
その「なぜ」の部分こそが、読み手にとって最も心に残る部分です。
それを一番よく知っているのは、他でもないあなたの会社の現場。
- 日々の業務で気づいたこと
- 顧客との会話
- 改善の小さなメモ
それらすべてが、次のコンテンツの「ネタの種」になります。
素材集めとは、特別な調査でも、派手な取材でもありません。
目の前の現場にある経験をすくい上げ、そこに宿る知恵を、読者の言葉に変えていくこと。その積み重ねこそが、信頼されるコンテンツを育てる唯一の道です。
だからこそ、明日からは「記事のために情報を探す」のではなく、「日々の中にある素材を言葉にする」視点で、社内を見てください。
あなたの現場には、すでに価値あるストーリーが、静かに眠っています。
【参考文献】デジタルマーケの成果を最大化するWebライティング(日本実業出版社)
記事制作代行なら横浜のクオリティロードへ

このように、質の高いコンテンツ制作の重要性が高まる中、私たちクオリティロードは、単なる記事作成に留まらない、総合的なコンテンツ支援サービスを提供しています。
クオリティロードの強み
まず、私たちの最大の特徴は、企業さまの課題やニーズを深く理解することから始めるアプローチにあります。
御社のビジネスの魅力を最大限に引き出すため、まずはじっくりとヒアリングを行い、最適な記事制作プランをご提案いたします。
たとえば、以下のような点について、くわしくお伺いしています。
- どのような読者に向けて情報を発信したいのか
- コンテンツを通じて何を実現したいのか
- 現在のサイト運営における課題は何か
- 競合他社との差別化ポイントは何か
SEOに強いコンテンツ制作
私たちの記事制作担当は、SEOの専門知識を持つライターが中心となって、検索エンジンと読者の双方に評価される記事を作成します。
お客さまのウェブサイトを詳細に分析し、効果的なキーワード選定から、読者の心に響く文章作成まで、一貫して対応いたします。
ワンストップサービスの提供
企画から取材、執筆、編集まで、すべてのプロセスを丁寧に行います。
また、ホームページのコンテンツだけでなく、チラシやパンフレットなどの紙媒体の制作にも対応しており、統一感のあるブランディングを実現できます。
お客さまは日々の業務に集中していただき、記事の更新は私たちにお任せください。
定期的な報告会で進捗状況や成果をご確認いただきながら、継続的な改善を図ってまいります。
お問い合わせはお気軽に
まずは無料相談から承ります。御社の課題やご要望をお聞かせください。私たちの経験と専門性を活かし、最適なコンテンツ制作プランをご提案させていただきます。
心を一つにして御社のビジネスの成長をサポートしてまいります。質の高いコンテンツで、新たな可能性を切り開きませんか?
ご興味のある方は、以下のバナーから詳細をご覧ください。