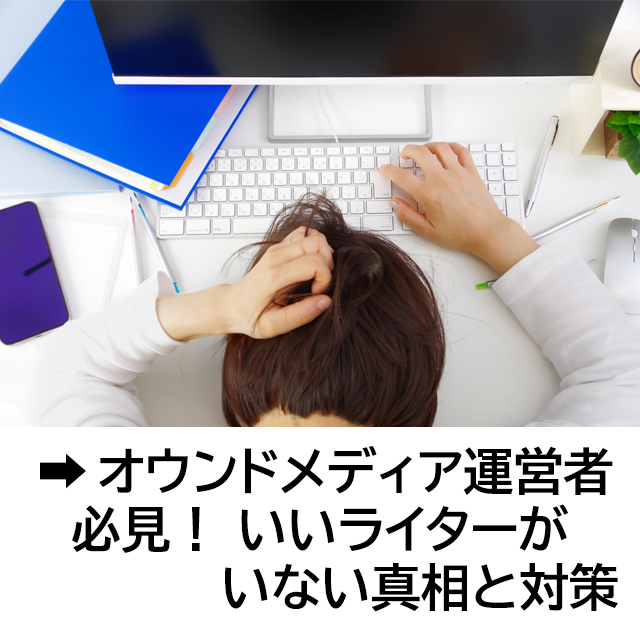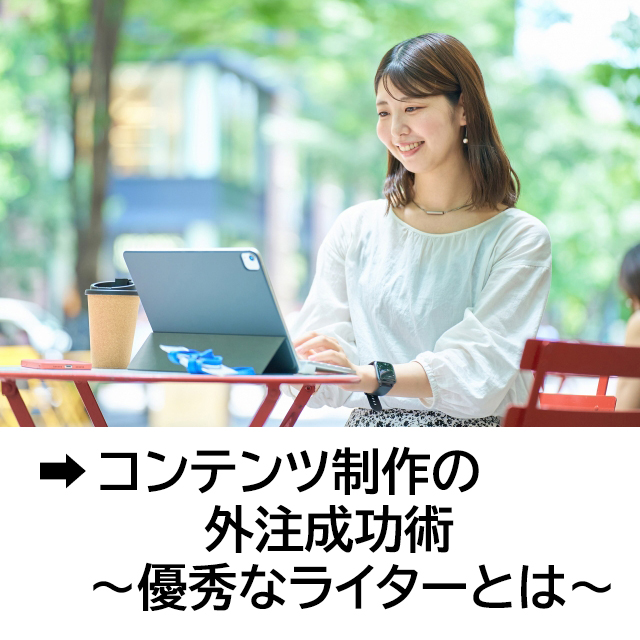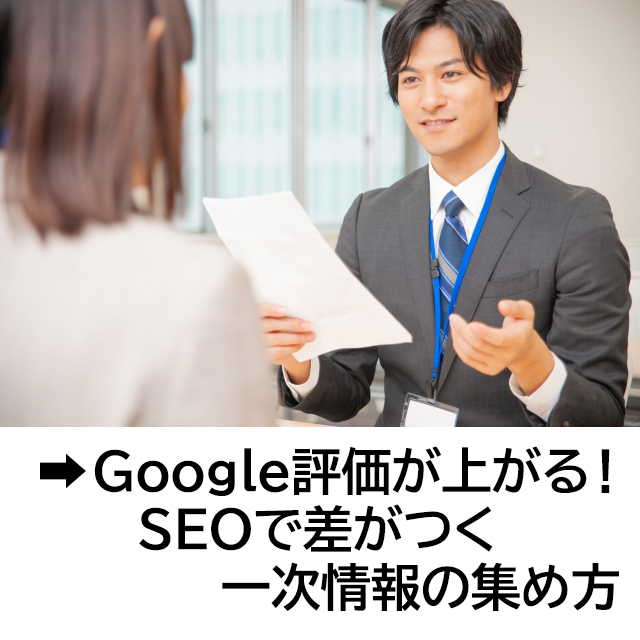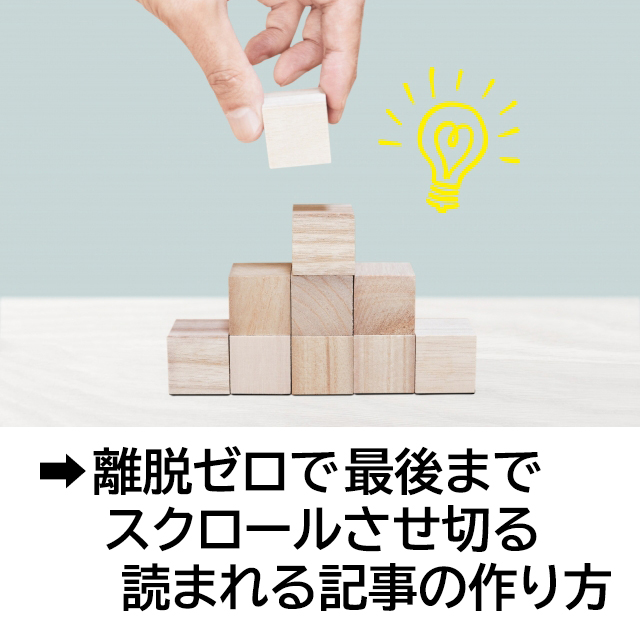検索1位を狙う! 構成で変わるSEOライティング術
オウンドメディアの記事を作るとき、
「どんな流れで書けば、ちゃんと伝わる記事になるんだろう?」
そんなふうに迷ったことはありませんか?
実は、記事の「伝わりやすさ」や「成果の出やすさ」は、書く前の「構成づくり」でほとんど決まります。
どれだけ良い素材があっても、構成があいまいなままだと、読者にも、検索エンジンにも、あなたの意図が届きにくくなってしまうんです。
とくに、外部ライターに依頼したり、社内のメンバーと分担して記事を作るときには、「構成案」を共有できているかどうかで、仕上がりの質も、成果の出方も大きく変わってきます。
この記事では、そんな「記事構成」の基本を、オウンドメディアの担当者さんに向けて、できるだけやさしく、わかりやすく整理していきます。
- 記事の目的をどう決めるか。
- 読者の検索意図をどう読み取るか。
- どんな手順で構成案を作ればいいのか。
この流れを押さえておけば、次に記事を企画するとき、もう迷うことはありません。
あなたの頭の中に「構成の地図」ができれば、どんなテーマの記事でも、きっとスムーズに形にできるはずです。
記事構成の作り方 ビジネス目的と成果指標を定義する

記事の構成を考えるとき、いちばん最初に決めておきたいのが「この文章を、何のために書くのか」です。
ここでいう「何のために」とは、単に「アクセスを増やしたい」や「読まれたい」という願いではなく、もっと具体的なビジネス上の目的のこと。
たとえば、
- 自社サービスの問い合わせを増やしたい
- ブランドを知ってもらいたい
- 採用ページへの導線を作りたい
など、会社として「どんな成果を得たいか」を明確にすることから、構成づくりは始まります。
書くこと=伝えることではなく、書くこと=成果へ導く設計だと考えてみてください。
次に決めておきたいのが、「どんな数字で成果を測るか」です。
これはいわゆるKPI(重要指標)と呼ばれるもので、記事を公開したあとに「うまくいったかどうか」を判断する基準になります。
たとえば、
- 資料請求の件数(CV=コンバージョン数)
- セミナー申込数
- 滞在時間や直帰率
- SNSでのシェア数
など、目的に合った指標を最初に決めておくことで、「やりっぱなしの記事」にならず、改善の軸が見えてきます。
数字だけを見ると少し堅く感じるかもしれませんが、この「目的とKPI」を先に決めておくことで、記事全体のトーンや流れ、使う言葉の温度まで自然と整ってくるんです。
そしてもうひとつ大切なのが、「誰に向けて」「どこから読まれるのか」を整理しておくこと。
つまり、想定読者と流入元を具体的に描くことです。
- 「誰に」=どんな立場・状況の人に読んでほしいのか。
- 「どこから」=検索から来るのか、SNSからなのか、メルマガなのか。
この2つを決めておくと、記事の語り口や構成の深さがぐっと明確になります。
たとえば、SNSからの流入が多い記事なら、冒頭で共感を引き出すような柔らかいトーンが向いていますし、検索流入を狙う記事なら、課題解決型の構成が効果的です。
どちらも「誰に届けるのか」を決めることで、文章の重心が自然と定まります。
ここまでのポイントをまとめると、構成を考える前に決めておくべきは、たった4つです。
1.何のために書くのか(目的)
2.どんな成果を目指すのか(KPI)
3.誰に届けたいのか(想定読者)
4.どこから読まれるのか(流入元)
この4つを決めてから構成に入ると、記事の一文一文に「意味」が生まれます。
構成とは、ただ章立てを考える作業ではなく、企業の目的と読者の出会いを設計すること。
この考え方を最初に持っておくと、どんなテーマでも、迷いのない構成づくりができるようになります。
SEOライティング × 検索意図の深掘り 読者目線で構成を設計する

記事の目的を決めたあとは、次に考えたいのが「読者は、どんな気持ちでこの記事にたどり着くのか」という部分です。
同じテーマでも、読む人の状況や心の温度によって、知りたいことはまったく変わります。
たとえば「SEOとは?」と検索する人と、「SEO 記事構成 作り方」と検索する人では、求めている深さも、知りたい内容も違いますよね。
ここで大事なのは、「読者の検索意図を立体的にとらえる」という視点です。
検索意図を深掘りするために、おすすめなのが「5つの問い」を立ててみることです。
1.いつ ── 読者はどんなタイミングでこのテーマを調べているのか
2.どこで ── どんな場所・環境で読んでいるのか(通勤中?オフィス?)
3.誰が ── 初心者なのか、担当者なのか、意思決定者なのか
4.どんな状況で ── どんな悩みや課題を抱えているのか
5.どうしたいか ── 記事を読んだあと、どんな行動を取りたいのか
この5つの問いを順番に考えると、「読者がいま、どのステップにいるのか」が見えてきます。
そして、その「位置」に合わせて構成を設計することが、読者にとって「ちょうどいい記事」をつくる第一歩です。
たとえば、「これから勉強を始めたい」段階の人には、専門用語を減らして、基本から説明する流れが親切です。
一方で、「すでに実践しているけど成果が出ない」人に向けるなら、つまずきやすいポイントを最初に示し、改善策を具体的に書く構成が響きます。
つまり、読者が「どの地点に立っているのか」を意識するだけで、見出しの順番も、内容の深さも自然に変わるのです。
検索意図とは、単なるキーワード分析ではなく、「読者の行動設計図」そのものなんですね。
ここで、第1章で決めた「目的」とつなげてみましょう。
たとえば企業側の目的が「問い合わせ数を増やす」だった場合、読者がどんな段階でその記事を読むのかを考えると、必要な内容の「粒度」が見えてきます。
- まだサービスを知らない人には「課題の共感と解説」
- 比較検討している人には「導入のメリットと具体例」
- 決断直前の人には「安心材料と行動への後押し」
このように、読者のステップを整理して構成を組むと、第1章で定めたビジネス目的が、自然に読者の行動と結びつきます。
つまり、企業視点の目的を、読者の物語に変換する作業こそが、SEOライティングの真髄なのです。
最後にもうひとつ。
検索意図をより正確に掴むために、検索上位の記事を観察することも大切です。
「どんな見出しが使われているか」
「どんな質問に答えているか」
「どんな順番で説明しているか」
これらを眺めるだけでも、ユーザーがどんな情報を期待しているかが見えてきます。
ただし、そのまま真似をするのではなく、「なぜこの見出しが上位にあるのか」を考えることが大切。
上位の記事の「構成の意図」を読み解いていくと、自分の記事に必要な要素と、足りない要素の両方が見えてくるはずです。
読者の意図を理解して構成を組むこと。
それは、読まれるためのテクニックではなく、「読者の心の動きを、文章でたどること」なんです。
第1章で決めた「企業の目的」と、第2章で見つけた「読者の目的」が重なる瞬間、はじめて記事は、伝わる力を持ちます。
その交わる地点を探すことが、構成づくりのいちばん大切な仕事なのかもしれません。
コンテンツ制作 × オウンドメディア運営 構成案を「素材リスト」として共有する

記事の構成を考えるとき、多くの人がやってしまいがちなのが、「構成案=ほぼ原稿の下書き」として作ってしまうこと。
けれど、本来の構成案は、「完成形」を描くための設計図ではなく、素材を整理するためのリスト」なんです。
構成案の段階で完璧に文章を書く必要はありません。
むしろ、どんな情報が必要かを「見える化」しておくことのほうが大事なんです。
たとえば、1つの見出しを作るときに考えたいのは、次のようなことです。
- この見出しで何を伝えたいのか
- その根拠となるデータや調査結果はあるか
- 補足する画像や図表が必要か
- 読者が「次に知りたい」と思う情報は何か
- その部分で紹介したいリンク(内部/外部)はどこか
- 読了後に読者へ促したい行動(CTA)は何か
これらを1つずつメモに書き出していくと、「今ある素材」と「足りない素材」がはっきりしてきます。
構成案とは、「情報の地図を描く作業」。
執筆の効率を上げるだけでなく、あとから加わるメンバーが内容を正確に理解する手がかりにもなります。
特に、外部ライターやデザイナーと一緒に進めるときには、この構成案が「共通言語」になります。
たとえば、次のような一枚のシートを共有するだけで、伝達のズレはぐっと減ります。
【構成案テンプレート(例)】
タイトル:〇〇〇〇〇〇〇
目的・KPI:〇〇(例:問い合わせ増加/資料DL)
想定読者:〇〇(例:中小企業の広報担当者)
流入元:〇〇(例:検索「〇〇とは」)h2-1:〇〇〇〇〇〇〇
目的:〇〇〇〇
必要素材:データ(〇〇調査)/図(フロー図)/CTA(資料DL)
内部リンク:〇〇〇〇h2-2:〇〇〇〇〇〇〇
目的:〇〇〇〇
必要素材:インタビュー引用/画像/CTA(問い合わせフォーム)
このように、「どの見出しに、どんな素材を配置するか」を一目で共有できるようにしておくと、ライターも編集者も「同じゴール」に向かって進めます。
構成案の目的は、「誰が見ても同じ記事をイメージできること」。
社内でも外部でも、関わる人が増えるほど、「伝わっていると思っていたこと」が伝わらなくなっていきます。
そんなとき、構成案が「意思の代弁者」になります。
- どんなトーンで書くのか。
- どんな順番で読ませたいのか。
- どんな感情を読者に残したいのか。
それらを一枚の構成シートに込めることで、全員が同じ方向を向いたコンテンツ制作ができるようになるんです。
そしてもう一歩進めるなら、構成案は「公開後の改善」にも使えます。
執筆前に決めた「素材」と「CTA」を後から見返せば、「どの要素が成果につながったか」「どこを直せばいいか」がすぐにわかります。
つまり構成案は、作って終わりではなく、成果を磨き続けるための羅針盤でもあるのです。
書く前に整える。書いたあとも活かす。
この「循環する構成案」の考え方を持つだけで、オウンドメディア全体の精度は、驚くほど変わっていきます。
まとめ 読みやすい記事作成は構成力で決まる

ここまで読んでいただいて、きっと感じていると思います。
「記事って、書く前がいちばん大事なんだな」と。
その通りです。
記事構成をしっかり整えることは、「書く作業」というよりも、成果を生み出すための設計づくりなんです。
記事づくりの流れをもう一度、シンプルに整理してみましょう。
1.目的を決める(企業としての狙いを明確に)
2.検索意図を深掘りする(読者の行動や心理を想像する)
3.素材を整理する(必要な情報・データ・画像を洗い出す)
4.共有する(チームで構成意図を合わせる)
この「目的 → 検索意図 → 素材 → 共有」という流れをひとつずつわけて考えるだけで、誰が関わっても記事の方向性がぶれなくなります。
たとえば、ライターが途中で変わっても、編集担当が別の人になっても、構成案さえ共有されていれば、品質は一定に保てます。
それが、オウンドメディアを「続けられる仕組み」の根っこなんです。
記事構成は、いわば「伝わる文章を支える土台」。
土台がしっかりしていれば、どんなテーマでも迷わずに書けるし、あとから何度でも修正・改善できます。
逆に、構成があいまいなまま進めてしまうと、読みやすさも、成果も、どこかで不安定になります。
だからこそ、書く前に立ち止まり、構成の段階で「この記事は誰に、どんな価値を届けたいのか」を言葉にしておくことが何より大切です。
次に記事を企画するときは、いきなり本文を書き始めるのではなく、まず「目的シート」と「構成表」を作ってみてください。
たったそれだけで、記事の完成までのスピードも、チーム全体の理解度も、見違えるほど変わります。
書く前に整理する時間は、遠回りではなく、最短ルート。
それが、「読みやすく伝わる記事」を生み出すための、いちばん確かな近道なんです。
構成力は、センスではなく習慣で磨かれます。
今日からの1本を、「構成から始める記事づくり」に変えてみませんか?
あなたのメディアが、読者にもっと届く場所へと育っていくはずです。
【参考文献】デジタルマーケの成果を最大化するWebライティング(日本実業出版社)
記事制作代行なら横浜のクオリティロードへ

このように、質の高いコンテンツ制作の重要性が高まる中、私たちクオリティロードは、単なる記事作成に留まらない、総合的なコンテンツ支援サービスを提供しています。
クオリティロードの強み
まず、私たちの最大の特徴は、企業さまの課題やニーズを深く理解することから始めるアプローチにあります。
御社のビジネスの魅力を最大限に引き出すため、まずはじっくりとヒアリングを行い、最適な記事制作プランをご提案いたします。
たとえば、以下のような点について、くわしくお伺いしています。
- どのような読者に向けて情報を発信したいのか
- コンテンツを通じて何を実現したいのか
- 現在のサイト運営における課題は何か
- 競合他社との差別化ポイントは何か
SEOに強いコンテンツ制作
私たちの記事制作担当は、SEOの専門知識を持つライターが中心となって、検索エンジンと読者の双方に評価される記事を作成します。
お客さまのウェブサイトを詳細に分析し、効果的なキーワード選定から、読者の心に響く文章作成まで、一貫して対応いたします。
ワンストップサービスの提供
企画から取材、執筆、編集まで、すべてのプロセスを丁寧に行います。
また、ホームページのコンテンツだけでなく、チラシやパンフレットなどの紙媒体の制作にも対応しており、統一感のあるブランディングを実現できます。
お客さまは日々の業務に集中していただき、記事の更新は私たちにお任せください。
定期的な報告会で進捗状況や成果をご確認いただきながら、継続的な改善を図ってまいります。
お問い合わせはお気軽に
まずは無料相談から承ります。御社の課題やご要望をお聞かせください。私たちの経験と専門性を活かし、最適なコンテンツ制作プランをご提案させていただきます。
心を一つにして御社のビジネスの成長をサポートしてまいります。質の高いコンテンツで、新たな可能性を切り開きませんか?
ご興味のある方は、以下のバナーから詳細をご覧ください。